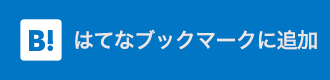「ひとりずつ」でしょうか、それとも「ひとりづつ」でしょうか。また、「少しずつ」でしょうか、「少しづつ」でしょうか
文章を書いているときなどに、この「ずつ」と「づつ」の使い方に迷うことってありますよね。
どちらかが間違いでしょうか。 それとも両方使えるのでしょうか。学校ではどう習ったのでしょう。
今回は、「ずつ」と「づつ」について解説していきます。
この記事の目次
「ずつ」と「づつ」正しいのはどっち?

学校で習ったのは「ずつ」?それとも「づつ」?
「ずつ」と「づつ」、学校で習ったのは、どちらかというと、
それは、
じつは、
年代によって異なります。
戦後、小学校に通った人は、「ずつ」と習っているはずです。
戦前はというと、一般的に「づつ」と習っていらっしゃいます。
文部科学省の『「現代仮名遣い」に関する内閣告示及び内閣訓令について』にも、「歴史的仮名遣い」として、 「一つづつ」と載っています。
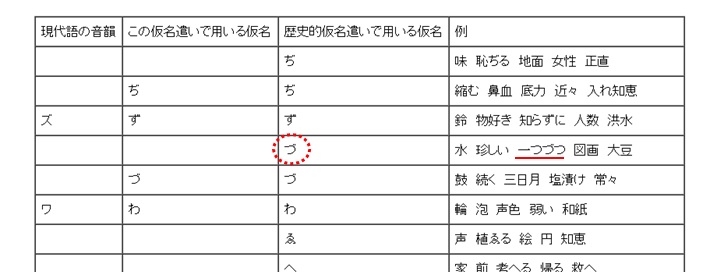
出展:文部科学省
「歴史的仮名遣い」とは?
「歴史的仮名遣い」とは、過去のある時期に決められた仮名の使い方です。
1946年(昭和21)に、「現代かなづかい」が公布されてからは,
「づつ」は、 おもに古典の表記にのみ使う、ということに使い分けがされてきました。
「づつ」は間違い?
現在「づつ」を使うのは間違いか、というとそうでもないのです。
1946年(昭和21)に公布された「現代かなづかい」が、40年後の1986年(昭和61)に、「現代仮名遣い」として改訂され、下の資料にあるように、「ずつ」は「づつ」を使うこともできる、ということになりました。
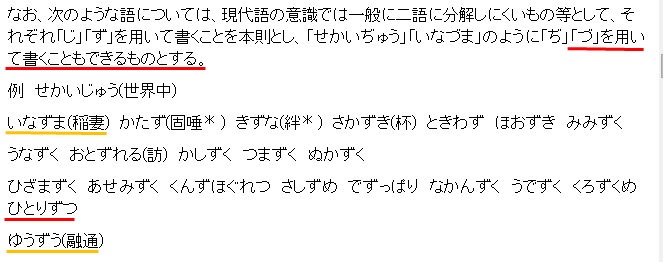
出展:文部科学省
「使うことができる」とされている「づつ」を使うか、本則にのっとって「ずつ」を使うかは、個人の自由、ということですね。
「ずつ」と「づつ」、違いはなに?
今、見てきたように「ずつ」と「づつ」に意味の違いはありません。
「ずつ」の意味は?
ところで「ずつ」の意味はというと、次の2つがあります。
① それぞれに等しく、その量を割り当てること。
例:子供たちに1パックずつ、いちごをあげた。
② 同じ量や程度が繰り返されること。
例:少しずつ、夜明けが近づいてくる。
「つくずく」?それとも「つくづく」?
「ず」を使うのか、「づ」を使うのか迷う場面って、今回の「ずつ」と「づつ」だけでは、ありませんよね。
たとえば、「つくずく」なのか「つくづく」なのか、「つれずれ」なのか「つれづれ」なのかで、迷ったことはありませんか。
「ず」と「づ」の使い方には、一応、決まりがあるのです。
本則は「ず」
先ほどの資料にもありますように、バラバラにできない2語、たとえば「稲妻」で「ズ」と発音するものは、基本的に「づ」ではなく、「ず」と書くことになっています。
「稲妻」は「稲(いね)」と「妻(つま)」ですが、バラバラにすると意味がなくなる語ですので、本則にのっとり「いなずま」と書く、
ということなのです。
「融通」は、「融(ゆう)」と「通(つう)」ですが、「ゆうずう」と書くのが一般的、ということです。
例外として「づ」と書くものもあります。
ただし、下の資料にありますように、 鼓や続くは「つづみ」「つづく」と書きます。
また、先ほどの「稲妻」と違い、 バラバラにしても意味が通るものに関しては、元のかなが「つ」ならば「づ」と書きます。
下の資料のオレンジ色で囲った言葉が、それにあたります。
「三日月(みかづき)」や「新妻(にいづま)」、「手作り(てづくり)」などです。
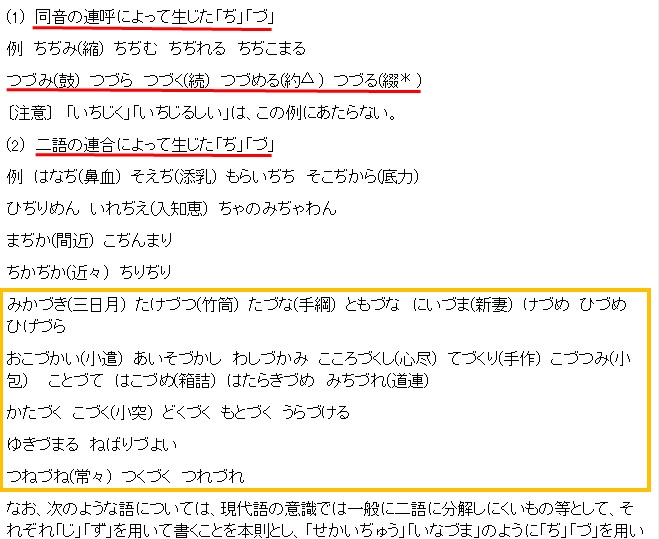
出展:文部科学省
まとめ
いかがでしたか。
「ずつ」と「づつ」、どちらも間違いではありません。
あなたはどちらをお使いになりますか。
日本語って、慣習が変わると使い方が変わったりしますので、混乱することもありますね。
頭を柔らかくしておいた方が、いいようです。
「十分」と「充分」の使い分けってあるのでしょうか。
「十分と充分の違いってなに?」
「すいません」と「すみません」の違いはなに?
「すいませんとすみません、どっちが正しいの?」
「に」と「で」の違いはなに?
「助詞の「に」と「で」の使い分けは?」
日本語を上手に使いこなせる外国の方って、天才だと思いません?^^